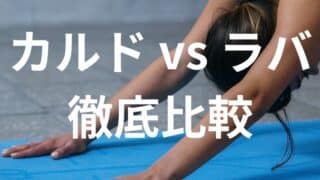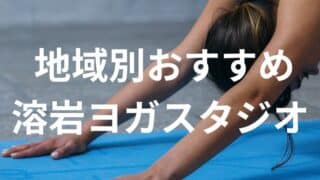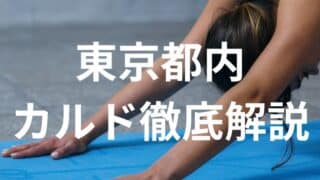この記事では、ヨガスートラのヨガ八支則をわかりやすく解説します。
ヨーガ哲学は、古代インドの精神的な教えであり、人間の本質や宇宙の秩序、人生の目的について深く考える学問です。
ヨーガ哲学では、人間の本質的な存在についての考え方が重要です。
人間は物質的な身体だけでなく、精神や意識の側面も持っているとされています。
また、ヨーガは「ヨーガ=統一」という意味を持ち、個人の心や意識を宇宙の意識と統合することを目指します。
ヨーガの根本的な目的は、個人の苦しみを解消し、真の幸福や自己の覚醒を追求することです。
このようなヨーガの哲学的な原則や教えは、主に「ヨーガ・スートラ」という古代のテキストにまとめられています。
ヨーガ・スートラは、パタンジャリという古代の哲学者によって纏められたもので、ヨーガの実践方法や心の状態に関する洞察を提供しています。
ヨガの教えには、八支則(はっしそく)という8つの段階の行法があります。
八支則は、パタンジャリが説いたヨガの聖典「ヨガ・スートラ」の中に出てくる、ヨガ哲学の基本的な教えの一つです。
「ヨガ・スートラ」とは紀元前3世紀頃~6世紀頃に書かれたヨーガについて理論的に解説した最古のテキストです。
この「ヨガ・スートラ」ですが、なかなか難解で、8つの段階の八支則を最初から順番に書いてあればわかりやすいのですが、第1章で第8段階であるサマディを解説しているので、ヨガ哲学初心者が最初から読むとよくわからなくなります。
そこで、ここではこの八支則について簡潔にわかりやすく解説します。
特に、八支則の最初の2段階であるヤマ・ニヤマ(10の教え)について詳しく解説しました。
なお、本記事は以下の2冊の書籍を参考にさせていただきました。
著者はリラヨガ・インスティテュートの乳井真介先生です。
リラヨガ・インスティテュートについての詳細は リラヨガ・インスティテュートまたは、以下の公式サイトを参考にしてください。
アンダーザライトの向井田みお先生が書かれた本でヨガ哲学のベストセラー本になっています。
アンダーザライトでは無料セミナー(不定期で 向井田みお先生のセミナーもやっています)も行っており、 無料セミナーに参加するとヨガクラスの無料招待券2枚がもらえます!
ヨガ・スートラとは?
ヨーガ・スートラは、紀元前200~400年頃に編纂されたとされる古代インドの教典で、ヨーガの理論と実践を体系化した重要な書物です。
その内容は、瞑想や心の制御を通じて解放(解脱)を目指すための哲学と実践法を示しています。
この教典は、約200の短い節(スートラ)で構成されており、ヨーガの基本原則や実践法、哲学的背景が簡潔に記されています。
特に、ヨーガ・スートラの中心的なテーマとして挙げられるのが「八支則」で、これは心身の調和と自己実現への道筋を具体的に示しています。
ヨーガ・スートラの目的
ヨーガ・スートラの目的は、瞑想や自己探求を通じて「心の働きを止めること(チッタ・ヴリッティ・ニローダハ)」を達成し、個人が本来の自己(プルシャ)と合一することです。
この状態に到達することで、執着や苦しみから解放され、精神的な自由を得られるとされています。
著者:パタンジャリ
ヨーガ・スートラの著者とされるパタンジャリは、「ヨーガの父」として広く尊敬されていますが、その生涯については詳細な記録がほとんど残されていません。
パタンジャリはヨーガの理論と実践を体系化し、後世のヨーガ哲学や瞑想の実践に大きな影響を与えました。
彼の教えは、現代でも世界中でヨーガを学ぶ人々に指針を提供しています。
ヨーガ・スートラの構成
ヨーガ・スートラは4つの章(パーダ)に分かれています:
- サマーディ・パーダ(瞑想への道)
- 瞑想の目的と方法、心の働きを超えるプロセスを解説。
- サーダナ・パーダ(実践の章)
- 八支則を中心に、実践の詳細が述べられています。
- ヴィブーティ・パーダ(超能力の章)
- ヨーガによる集中と超越的な力について説明。
- カイヴァリヤ・パーダ(解脱の章)
- 完全な自由と精神的解放について述べています。
ヨガ八支則とは?
ヨガ八支則は、古代インドの教典「ヨーガ・スートラ」において、心と体を調和させ、精神的な成長を目指すための8つのステップとして詳しく説明されています。
ここではヨガ八支則について詳しく解説します。
ヨーガ・スートラと八支則の関係
「ヨーガ・スートラ」は、ヨガの理論と実践を体系的にまとめた古代インドの教典であり、その中で八支則は非常に重要な位置を占めています。
八支則は、ヨーガ・スートラの第2章「サーダナ・パーダ」で具体的に解説されており、ヨーガの実践者が心と体を整え、精神的な成長を遂げるための8つの段階を示しています。
この8つのステップは、日常生活における実践を通じて悟りに近づくための道しるべとなります。
なお、上述したようにヨーガ・スートラ全体は4つの章に分かれており、八支則はその中でも第2章で重要な役割を果たします。
第1章ではヨーガの目的や心の働きについて、また第3章では集中と超越的な力について、最後の第4章では解脱に至る道が語られていますが、八支則は主に第2章において実践的な方法として詳細に説明されています。
ヨガ八支則の8つのステップ
八支則は、心と体を調和させ、精神的な解放を目指すための8つの段階から成り立っています。以下がその詳細です:
- ヤマ(禁戒)
他人との関係における道徳的な行動規範。非暴力や正直など、5つの原則を実践します。 - ニヤマ(勧戒)
自己との関係における内的な規律。清浄や自己鍛錬など、内面的な成長を促します。 - アーサナ(座法)
瞑想のための身体的な姿勢を整える。身体を柔軟に保ち、心の安定を図ります。 - プラーナーヤーマ(呼吸法)
呼吸を制御し、生命エネルギー(プラーナ)を調和させることで、心と体の調和を保ちます。 - プラティヤハーラ(制感)
外部の刺激から感覚を制御し、内面的な集中力を高めます。 - ダーラナ(集中)
一点に意識を集中させ、心を落ち着けます。 - ディヤーナ(瞑想)
持続的な集中状態を作り、精神的な平和を保ちます。 - サマーディ(三昧)
自己と宇宙が一体化する究極の境地であり、解脱(カイヴァリヤ)とも呼ばれる状態です。
八支則を実生活に活かす方法
八支則は、ヨーガの理論に基づいた実践的なアプローチであり、日常生活にも応用可能です。例えば、ヤマ(禁戒)の実践により、人間関係がより平和的になり、ニヤマ(勧戒)を通じて自己成長が促進されます。
また、アーサナ(座法)やプラーナーヤーマ(呼吸法)を実践することで、身体の柔軟性や健康が改善され、精神的な安定を得ることができます。
ヨーガ八支則は、ヨーガ・スートラの中で、実践的に心身の調和を図り、精神的な解放を目指すための最も重要な手段とされています。
第2章「サーダナ・パーダ」で詳細に述べられており、これを実践することで、日々の生活においても悟りへの道が開かれるとされています。
八支則は、現代においても自己成長やストレス管理、心の平穏を求めるための有益な指針となるでしょう。
実践者にとって、その哲学は深い洞察を与えるものです。
ヤマとは?【八支則の第一段階】

ヨーガ八支則の第一段階は「ヤマ」です。
ヤマは「禁戒」と訳され、5つの「してはならない」行動規範を示しています。
これらは日常生活で避けるべき行いを定め、他者や社会との調和を保つための基礎的な教えです。以下がヤマの5つの原則です。
ヤマの5つの原則
- アヒムサ(Ahimsa)非暴力、不殺生
- 暴力を避けるだけでなく、言葉や思考レベルでも他者を傷つけないことが求められます。
- サティヤ(Satya)正直、嘘をつかない
- 言葉に責任を持ち、思考・言葉・行動の一貫性を保つことが正直さの本質です。
- アスティヤ(Asteya)不盗
- 他人の所有物や時間、信頼を奪わないこと。物理的な盗みだけでなく、精神的な所有欲も戒めます。
- ブラフマチャリヤ(Brahmacharya)禁欲
- 欲望をコントロールし、エネルギーを無駄に消耗しない。特に性的欲求の制御が中心です。
- アパリグラハ(Aparigraha)不貪
- 必要以上に物を求めず、執着を手放すことで心の平穏を得ることを目指します。
日頃の努力で、上記のヤマ(気をつけるべきこと)が自分の習慣となり、考えなくてもあたりまえのように自分の行動がいつも正しくあるようになるまで続ければ、必ず心の浄化という結果は現れます。
アヒムサ(非暴力・不殺生)
ヤマの最初の戒律はアヒムサ(非暴力)です。
パタンジャリは、まずこのアヒムサを実践することを私たちに奨励しています。
暴力と聞くと、殴る、蹴るなどの肉体的な暴力が真っ先に思い浮かぶかもしれません。
しかし、アヒムサという戒律が戒めているのは、単に肉体的な暴力だけではありません。
身体、言葉、思考レベルでの非暴力
ヨーガでは、私たちが何かを行うとき、「思い(意)のレベル」「言葉(口)のレベル」「身体(身)のレベル」の3つのレベルで考えます。
これらのすべてにおいて非暴力を実践する必要があります。
- 身体的な暴力
他者に直接的な害を与える行動を避けます。殴る、蹴るといった肉体的な暴力を振るわないのは当然のことです。 - 言葉の暴力
感情に任せて口汚い言葉を使い、他者を傷つける行為を戒めます。言葉の暴力は時に肉体的な暴力以上に深い傷を残すことがあります。 - 思考の暴力
心の中で怒りや憎しみを抱くことも暴力と見なされます。たとえ行動や言葉に表れなくても、心の中で暴力的な感情が渦巻いている状態は、意識のエネルギーを乱し、周囲に悪影響を及ぼします。
アヒムサの実践
アヒムサを実践するためには、これらの3つのレベルすべてで非暴力を徹底する必要があります。
たとえ肉体的な暴力を振るわなくても、心の中で暴力的な思いを抱いていれば、それも暴力にあたります。
言葉や身体のレベルで非暴力を実践できるようになったとしても、心の中の暴力まで制御するのはさらに難しい挑戦です。
しかし、パタンジャリは「心のレベルまで暴力を完全に制御することができた時、すべての敵対が止む」と断言しています。
敵対が止むとは?
「敵対」とは、相反するもの同士がぶつかり合うことで生じる争いや対立を指します。
たとえば、誰かが自分に向かって怒りを込めた言葉を言ったとき、私たちは無意識にその言葉を押し返そうとしてしまいます。
このように、互いに力を押し合うことで敵対心が生まれ、さらなる争いを引き起こします。
アヒムサの戒律を思い出し、冷静に判断して自分の怒りや暴力的な感情を抑えることができれば、このような対立を回避することができます。
自分の内側に非暴力を徹底することで、周囲との調和を自然に築くことができるのです。
サティヤ(嘘をつかない)
ヤマの2つ目の戒律はサティヤ(Satya)です。
サティヤとは、「嘘をつかない」「正直である」ということを意味します。ただし、ここでの「正直」とは単なる誠実さを超えた深い意味を持っています。
それは、自分の使う言葉に一貫性を持たせ、言葉に対して尊敬の念を払うことを求めています。
嘘とは何か?
嘘とは何でしょうか?
多くの場合、私たちは「嘘つき」と聞くと、言葉にしたことを実行しなかったり、事実と異なることを言う行為をイメージします。
- 言ったことを守らない嘘
- 例: 「明日やる」と言って実行しない。これは言葉と行動の整合性が取れていない状態です。
- 思考と言葉が一致しない嘘
- 例: 「調子が悪いので」と嘘をついて本当の理由を隠す場合、心(思い)と言葉が一致していないため、ヨーガ的には嘘とみなされます。
ヨーガ的な嘘の捉え方
ヨーガでは、嘘を「意(思考)」「口(言葉)」「身(行動)」の3つのレベルで捉えます。この3つの整合性が保たれていなければ、それは嘘として扱われます。
たとえば、気の進まない食事の誘いを断る際、「調子が悪い」と言えば、心で感じている状態と言葉が一致していないため、矛盾が生じます。
このような場合には、相手を傷つけない配慮をしながらも、「今日は用事があります」と答えるのが正直な対応です。
サティヤの実践例
サティヤの実践では、思考と言葉、行動が常に一致するように心がけます。
- 言葉を選ぶ
正直であることと、相手を傷つけないことのバランスを取ります。- 例: 「あなたと食事に行きたくない」と直接伝えるのではなく、「今日は予定があるので」と答える。
- 行動を一致させる
言葉にしたことを行動に移すことで、信頼を築きます。- 例: 約束を守る、発言に責任を持つ。
嘘を避けることで得られる力
サティヤを守ることで得られるのは、言葉そのものの力です。
スートラには、「嘘をつかないことを守り抜けば、その人の発言すべてが現実になる」とあります。
これは、言葉と思考、行動が一致している人の言葉には、現実を形作る力が宿るという教えです。
私たちは嘘に敏感です。
心の中で嘘がある人には不信感を抱き、自然と距離を置きます。
一方で、意(思考)、口(言葉)、身(行動)が一致している人には、信頼感や安心感を覚えます。これがサティヤの本質です。
サティヤの意義
サティヤは単なる「嘘をつかない」という教えではなく、思考、言葉、行動の整合性を保つことを通じて、自己の内面を浄化し、他者との調和を築くための戒律です。
これを日々実践することで、言葉に力が宿り、未来を具体化する力を得ることができます。
アスティヤ(不盗)
アスティヤ(Asteya)は「不盗」を意味します。
これは文字通り「他人のものを盗まない」という教えですが、その範囲は物質的な所有物にとどまりません。
他人の時間、信頼、権利、利益を奪うこともアスティヤに反する行為とされます。
アスティヤの具体例
アスティヤを実践するには、以下のような状況を意識して行動することが重要です。
- 物理的な盗みを避ける
他人の物を無断で使う、返さない、または奪うことをしない。 - 時間の盗みを避ける
遅刻や行列への割り込み、相手の話を遮るといった行為は、他人の時間を奪う行為とされます。これもアスティヤに反します。 - 信頼を守る
約束を破る、秘密を漏らすなど、他人の信頼を裏切る行為を避ける。
スートラの教え
スートラには次のようにあります。
「人の物を盗らないことが習慣になったとき、自分にとって本当に大事なものがすべて手に入る。」
この教えは、他人のものを盗む行為は不安や罪悪感を生み、自分の心の平安を失わせるということを示しています。
反対に、アスティヤを守り、欲望や執着を手放すことで、必要なものは自然に自分のもとにやってくるとされています。
家族や親友であっても、他人の所有物を盗むことで信頼を失い、長期的には不安に縛られる恐れがあります。
アスティヤはこうした不安を根本から取り除き、心の自由を得るための教えなのです。
ブラフマチャリヤ(禁欲)
ブラフマチャリヤ(Brahmacharya)は「禁欲」を意味します。
この戒律は単なる性的欲望の抑制だけでなく、欲望全般を適切に制御し、自分のエネルギーを有効に活用することを教えています。
ブラフマチャリヤの語源と背景
ブラフマチャリヤは2つの言葉から成り立っています。
- ブラフマン: 万物の背後に存在する神聖な力。
- アーチャリヤ: 規範を守る者。
この戒律は古代インドでは「性的禁欲」として知られ、特に男性ヨーギにとって重要な教えでした。
当時、性的欲望に溺れることで生命エネルギーが浪費され、有意義な活動が行えなくなると信じられていたからです。
現代におけるブラフマチャリヤの実践
現代では、「禁欲」の意味がより広がりを持ち、次のような形で実践されています。
- 性的欲望の制御
パートナー以外との不必要な関係を避ける。また、性的欲望に振り回されず、エネルギーを有効活用する。 - 規則正しい生活
夜更かしや過剰な飲食を避け、健康的でバランスの取れた生活を送る。- 例: 朝早く起き、集中力を高める活動に時間を使い、夜は十分な休息をとる。
スートラの教え
スートラには次のように記されています。
「規則正しい生活ができるようになると、精神的な力と目標を達成する強さを得る。」
欲望をコントロールし、エネルギーを浪費しないことで、自分の中に隠れた力を引き出し、目標達成や精神的な成長を促すことができます。
アパリグラハ(不貪)
ヤマの5つ目の戒律はアパリグラハ(Aparigraha)です。
この教えは「必要以上のものを求めないこと」「執着を手放すこと」を意味します。
アパリグラハの具体例
- 物質的な所有の節制
必要以上に物を持たず、シンプルな生活を心がける。- 例: 衝動買いや過剰な所有を避けることで、心の平穏を得る。
- 執着の解放
他人の成功や物に対する嫉妬を手放し、自分に与えられたものに感謝する。
スートラの教え
パタンジャリは次のように述べています。
「執着を手放せば、必要なものが自然と自分のもとにやってくる。」
執着は、心を不安定にし、不必要なストレスや嫉妬を生みます。
アパリグラハを実践することで、外的な所有に縛られず、内なる満足感と調和を得ることができます。
必要以上のものに執着せず、シンプルな生活を送ることで、真の自由と幸福を見つけることができます。
「手放す」「執着しない」という教えはアッビャーサ(修習)とヴァイラーギャ(離欲)とは?で詳しく解説しています。
アパリグラハの現代的な意味
この教えは、断捨離やミニマリズムの精神にも通じます。
これらの戒律は、他者との調和を保つだけでなく、自分自身の内面を浄化し、精神的な成長を促します。
それぞれの戒律を日々の生活に取り入れることで、より満たされた人生を送ることができるでしょう。
ニヤマとは?【八支則の第二段階】

ヨーガ八支則の2段階目にあたる「ニヤマ」は、日本語で「勧戒」と訳されます。
ニヤマは、日常生活で実践すべき5つの行いを指し、自己の内面を整えるための具体的な指針を提供しています。
この戒律は、外的な行動を規制するヤマ(禁戒)に対し、内面的な修養を深め、心と体の調和を図ることを目的としています。
ニヤマの5つの原則
ニヤマには以下の5つの教えがあります。それぞれが、ヨーガの実践者に必要な心の姿勢や生活習慣を示しています。
- シャウチャ(清浄・浄化)
- サントーシャ(満足・知足)
- タパス(苦行・自制)
- スヴァディアーヤ(読誦・学習)
- イーシュワラ・プラニダーナ(信仰)
シャウチャ(清浄・浄化)
シャウチャは「清浄」「浄化」を意味します。
この教えは、身体、心、環境のすべてを清潔に保つことを奨励しています。
シャウチャの背景と意義
ヨーガの哲学では、外的な清潔さと内的な清浄さは密接に関連しているとされています。
たとえば、散らかった部屋や汚れた衣服は心の状態を反映すると考えられています。
環境や身体を清潔に保つことで、心も落ち着き、前向きなエネルギーを得ることができます。
シャウチャの具体例
- 身体の清潔
- 衣服を洗う、髪を整える、入浴をするなど、身体を清潔に保つこと。他人に不快感を与えないことが重要です。
- 環境の清潔
- 部屋を整理整頓し、不要なものを取り除くことで、集中力を高めることができます。
- 心の浄化
- 嫉妬や怒りといったネガティブな感情に執着せず、それらを手放す努力をします。たとえば、呼吸法や瞑想を通じて心をリフレッシュする方法が有効です。
シャウチャの効果
シャウチャを実践することで、周囲に調和をもたらし、自分自身も健やかな心と体を保つことができます。清潔さは、ヨーガの他の実践を深めるための基盤となります。
サントーシャ(満足・知足)
サントーシャは「満足」「知足」を意味し、現状に感謝し、与えられたものに満足することを教えています。
サントーシャの背景と意義
私たちはしばしば「もっと欲しい」と思いがちです。
しかし、足りないものに目を向け続けると、欠乏感や不満が心を支配します。
サントーシャは、今あるものに感謝し、自分の内面に幸せを見つける態度を養う教えです。
サントーシャの具体例
- 困難を成長の糧にする
- 目の前の困難や課題を「自分を鍛える機会」と捉えます。変えられないものを受け入れ、変えられるものは勇気を持って変えましょう。
- 今あるものを感謝する
- 健康、人間関係、環境など、当たり前に思えるものにも感謝します。たとえば、普通に歩けることが特別な幸せだと気づくこともその一例です。
- 過剰な欲望を手放す
- 新しい物を買い続けることや、他人との比較をやめ、自分にとって本当に必要なものを見極めます。
サントーシャの効果
仏陀も「真の幸福は、足りないものではなく、今あるものへの感謝から生まれる」と説いています。
サントーシャを実践することで、環境や状況に左右されない心の平穏を得ることができます。
タパス(苦行・自制)
タパスは「苦行」「自制」を意味します。
これは、自らの成長のために困難を積極的に受け入れ、努力を続ける姿勢を教えています。
タパスの背景と意義
人は予想外の出来事や試練に直面すると、苦しみを感じます。
しかし、こうした状況を克服することで自分の許容範囲を広げ、強さを培うことができます。
タパスは、心身を鍛えるための忍耐力と努力の重要性を説いています。
タパスの具体例
- 困難を受け入れる
- たとえば、厳しいトレーニングや難しい課題に挑むことで、精神的な強さを得ます。
- 自分を傷つけない苦行
- タパスは自己成長を目指すものであり、自分を無理に痛めつけることではありません。過度な我慢や自己否定はアヒムサ(非暴力)に反する行為です。
- 習慣を改善する
- 夜更かしを避け、早寝早起きを習慣にすることや、適切な食事を取ることもタパスの一環です。
タパスの効果
タパスを実践することで、自分自身に対する信頼感が高まり、困難を乗り越える力が培われます。これにより、精神的な成長と安定を得ることができます。
スヴァディアーヤ(読誦・学習)
スヴァディアーヤは「読誦」「学習」を意味します。
これは、自分を成長させる知識を学び、内省を深めることを教えています。
スヴァディアーヤの具体例
- 聖典や名著の読書
- 聖典や人格者が書いた本を読むことで、心を清め、善い方向へ導きます。
- 自己内省
- 学んだ知識を日常生活に活かし、実践を通じて智慧に昇華させます。
イーシュワラ・プラニダーナ(信仰)
イーシュワラ・プラニダーナは「信仰」を意味し、神や宇宙の根源的な力に感謝と信頼を寄せる教えです。
イーシュワラ・プラニダーナの具体例
- 自然や宇宙の力を受け入れる
- 自分では変えられないものを受け入れ、流れに身を任せる心を養います。
- 感謝と祈り
- 自分の中に宿る神性を信じ、祈りや感謝の心を持ちます。
ニヤマは、自分自身を深く見つめ、心と体の浄化を目指す教えです。
それぞれの戒律を日常生活に取り入れることで、内面的な平和と調和を得ることができます。
清浄、知足、苦行、学習、信仰という5つの行いを実践し、より充実した人生を送りましょう。
アーサナとは?【八支則の第三段階】

ヨーガの八支則の第三段階はアーサナ(Asana)です。
今ではアーサナといえば、ポーズのことをいいますが、もともとは単なるポーズではなく、瞑想を行なう・深めるための座法のことを指します。
様々なポーズの実践により、体を鍛錬し、長時間の瞑想に耐えうる状態をつくり、また、心と体はつながっているので、身体能力の向上は、心の調整にもつながります。
ポーズは、安定していること、快適であることが理想です。
そして、冷静かつ客観的に、自分の身体感覚や心の状態を観察し、他者と自分を比べたり判断することなく、こだわりをなくし、その空間と一つとなるような感覚で集中しましょう。
プラーナヤーマとは?【八支則の第四段階】
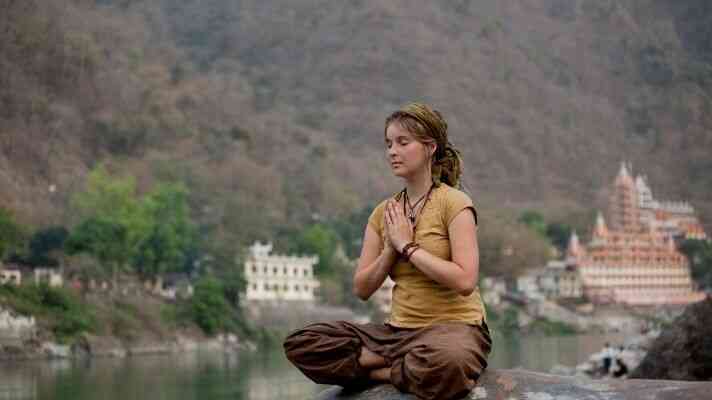
ヨーガの八支則の第四段階はプラーナヤーマ(Pranayama)です。
プラーナヤーマとは、呼吸法・調気法と訳され、「プラーナ」は生命エネルギーのことで、「プラーナヤーマ」は、呼吸をコントロールすることによって、体内の見えないエネルギーを調整することを示します。
呼吸と心と体の状態はつながっていて、呼吸が落ち着いて安定してれば心も穏やかで、体はリラックスします。
呼吸のもうひとつの目的は、血液や脳により酸素や影響を与えることです。
なお、理想的に呼吸を深めていくためには、正しい姿勢を心がけることが必要です。
プラティヤハーラとは?【八支則の第五段階】
ヨーガの八支則の第五段階はプラティヤハーラ(Pratyahara)です。
プラティヤハーラとは、感覚の制御と訳すことができ、感覚への意識を深め、繊細に感じることをいいます。
感覚を内側に向ける練習をしなければ、瞑想の境地に到達することはできません。
そのため外側に向いている五感の知覚を、内側に方向づけ、内的感覚を高めていきます。
ただ、感覚に意識を向け続け、アーサナを実践していても、感覚を我慢したり抑えつけたりするのではなく、それを感じている自分を常に冷静・客観視していくのです。
これは、日々起きてくる様々な出来事や問題に、感情を振り回されるのではなく、何が起ころうともブレない自分を作る精神の鍛錬につながります。
ダーラナとは?【八支則の第六段階】
ヨーガの八支則の第六段階はダーラナ(Dharana)です。
ダーラナとは、意識を特定の対象物に長時間留めておくことで、心が集中すればするほど、一点に向かう大きなパワーが生まれます。
つまり、今この瞬間に考えるべきでない雑念に意識を捕らわれないようにします。
部屋の中が綺麗なら仕事がはかどるように、心の中に様々な雑念がなければ、今本当に必要なことに全力を捧げることができます。
なお、第六段階の「ダーラナ」、第七段階の「ディアーナ」、第八段階の「サマーディ」は、区切りの付けられない一連の心の流れとなります。
ディアナとは?【八支則の第七段階】
八支則の第七段階はディアナ(Dhyana)です。
このディヤーナは一般的に「瞑想」と訳され、中国では「禅那」と呼ばれたりします。
中国から日本に渡り「禅」となりました。
仏教の〈禅〉は、このディアナが語源だといわれており、意識が積極的な努力なしに一方向に深く集中している状態をディアナといいます。
つまり、ディアナ(瞑想)とはプラティヤハーラ(感覚制御)とダーラナ(集中)が深まっている状態で、自分と他を分け隔てなくなった意識の状態で、雑念から解放された無我の境地を意味します。
無我夢中状態になると、意識のエネルギーと対象のエネルギーの波長がぴったり一致し、主観と客観の区別が消失します。
「波長が合う」といいますが、波長が合う人と一緒にいるとき私たちはまるでその対象が自分の一部になったかのような感覚を覚えます。
このとき、時間、空間を認識する「自分」という主体がなくなることで、あっという間に時間が過ぎていくのです。
したがって、この時間の流れがあっという間に感じることが、私たちがディヤーナに入ったという状態といえます。
私たちが何かの対象に集中すると、自然と呼吸数は減少します。
ヨーガではこのような強い集中状態によって自然と呼吸停止することを「ケーヴァラ・クンバカ」と呼びます。
高い集中状態によって対象と完全に波長を合わせると、その対象と戦うことにエネルギーを割く必要がなくなります。
このとき、脳はリラックスし、必要なのは身体の恒常性を維持するための必要最低限の酸素のみになります。
これによって呼吸数が減少し、新陳代謝のスピードも遅くなり、いわば冬眠に近い状態が生まれるのです。
新陳代謝が低下すると老化のスピードも緩やかになります。
反対に、私たち人間は、集中できずにイライラした状態のとき、呼吸は浅く、早くなっていきます。
このとき新陳代謝は高まり、老化も早く進みやすくなります。
つまり無我夢中に何事にも打ち込んでいる人の方が若さを保っており、反対に完璧主義ですぐイライラしてしまう人は老化が早くなるといえます。
サマーディとは?【八支則の第八段階】
八支則の第八段階はサマーディ(Samadhi)です。
サマーディとは三昧と訳され、「超意識、悟り」を意味します。
ダーラナで集中状態に入り、ディヤーナで集中状態をさらに高めることで、やがて集中状態が極限まで深まると、すべての意識は「今この瞬間」に注ぎこまれるようになります。
すると、意識と集中の対象物は完全に波長のあった状態になり、一体化します。
つまり、ヨガの最終目標である悟りの状態になります。
煩悩からの解放され、解脱した状態です。
瞑想がさらに深まり、集中の対象との一体感を感じている状態です。
この境地がヨーガの目指す最終目的地「サマーディ」です。
サマーディには「共に置く」という意味があり、これは「自分」と「自分以外の存在」を共に置くことで「完全なつながり」を示します。
サマーディに入ると、人は光のシャワーに包まれると言われます。
サマーディを日本語に変換した言葉が「三昧」です。
パチンコ三昧というと、集中の対象はパチンコ台で、高い集中状態で玉を打ち続けると、無我夢中状態に入り、人はサマーディ状態には入ります。
ゆえにサマーディも私たちの身近に起きている現象なのです。
人の集中状態は伝染します。
高い集中状態の人のそばでは集中力が増し、イライラした人のそばでは集中力が低下します。
ゆえに深いサマーディ状態の人のそばにいると、その深い集中状態は広がっていきます。
おわりに
ここでは、「ヨガ・スートラ」の八支則について解説しました。
噓をつかず常に誠実でいる、自分にとって必要・大事な物は向こうからやってくるため、わざわざ人の物を盗む行為をする必要がないこと、規則正しい生活をして生きていたら体が健康的になる以外に精神的な力と高い志・誘惑に負けない力がつく、執着のある人生を手放せば新しい知恵が生まれるなど、私たちが生きてくうえでも重要なことが示されています。
ヨガ・スートラはもっと深いものですので、以下で紹介する本を読んでぜひもっと深めてください。
なお、本記事は以下の2冊の本を参考にしました。
著者はリラヨガ・インスティテュートの乳井真介先生です。
乳井真介先生は日本のヨガの世界で有名な方で、ヨガ雑誌のヨギー二やヨガジャーナルにたびたび出演しています。
リラヨガ・インスティテュートのヨガ・インストラクター講師養成講座では乳井真介先生から直接レッスンを受けられます。
リラヨガ・インスティテュートについての詳細は リラヨガ・インスティテュートを参考にしてください。
アンダーザライトの向井田みお先生が書かれた本でヨガ哲学のベストセラー本になっています。
特に、アンダーザライトの「UTL YOGA ONLINE」ではほぼ毎朝向井田みお先生 がヨガ哲学のレッスンを行っております。
また、無料セミナー(不定期で 向井田みお先生のセミナーもやっています)も行っており、特に、無料セミナーに参加するとヨガクラスの無料招待券2枚と5,000円割引クーポンコードがもらえます!
アンダーザライトのRYT200にご興味のある方はアンダーザライトのインストラクター養成RYT200がオンライン受講可に!をご覧ください。
ヨガ哲学に関するその他のおすすめ記事